旬の食材とお料理方法:夏
食材を知りつくした、市場のプロが、旬の食材を美味しくいただくお料理方法をご紹介します。
皆さんが夏に食べたくなるお料理はなんですか?
暑い夏におすすめの夏バテを防ぐスタミナレシピから旬の食材を活かしたお料理を食材のプロがお届けします。。
牛肉(エスニックミートボールのトマト煮込み)
○ミートボール
タコシーズニング(市販の物) 大さじ2と1/2
お好みの挽き肉 300g
卵(小) 1個
しょうが(すりおろす) 1/3片
にんにく(すりおろす) 1/2片
ブラックベッパー 少々
玉ねぎ(くし形切り)1/2個
パプリカ 赤(くし形切り) 1個
オクラ 8本
トマト水煮 1缶
にんにく(みじんきり) 1片
チキンスープ(又は水)300cc
クミン(パウダー) 小さじ1
ブラックペッパー(あらびき) 少々
オリーブオイル 大さじ2と1/2
塩 適量
ミートボールの材料をすべてボウルに入れよく混ぜ合わせる。
オクラは、硬いヘタの部分をそぎ切りにする。トマト水煮はボウルに明けて手で握りつぶしヘタと目立つ筋を取り除く。
トマトソースを作る。鍋にオリーブオイルとにんにくを入れて熱して玉ねぎを加えて少し透き通るまで炒める。パプリカを入れ、サッと全体に油を回すように混ぜ合わせたら、トマト水煮とチキンスープを加えてごく軽めに塩を加える。
3が煮立ってきたら適当な大きさに丸めた 1を加え再び煮立ったらアクをとり、蓋をして15~20分煮る。2のオクラを加えてさらに2~3分加熱し、クミン、コリアンダー、ブラックペッパー、塩で味を調える


牛肉(カレー串焼き)
その1 材料 4人分
牛肉(薄切り) 400g
カレー粉 大さじ1
ウスターソース 大さじ2
塩、こしょう 各適量
オリーブオイル 適量
作り方
ボウルに牛肉、カレー粉、ウスターソース、塩、こしょうをいれよく混ぜ合わせる。
1を串に巻きオリーブオイルを熱したフライパンで焼く
その2 材料 4人分
牛肉(薄切り) 400g
おろしにんにく 1片
しょう油 大さじ1
ターメリック 大さじ1
砂糖 小さじ1
サラダ油、一味 少々
作り方
ボウルに牛肉、カレー粉、ウスターソース、塩、こしょうをいれよく混ぜ合わせる。
1を串に巻きオリーブオイルを熱したフライパンで焼く
アコウ
夏本番を迎え、脂がのってうまみを増すのが、夏の白身魚の横綱”アコウ”です。学名はキジハタで、クエなどの親類になり、関東でアコウと呼ばれるメバル科の赤魚とは全く別の魚です。
アコウは不思議な魚で小型のものはほとんどがメスで、大きく成長すると雄に性転換するといわれています。
温かく浅い海を好むため、私もダイビング中に出会ったことがありますが、ふっくらと肥えて、警戒心も少なく悠然と泳ぐ姿には、横綱の風格があります。
黒門市場には九州、和歌山方面などから入荷があり、大型のものの方が美味で高価になります。
身はキメが細かいので薄造りにしてポン酢か、氷水で洗いにしわさび醤油で、頭は、酒、砂糖、醤油であら煮にし、目や口の周りのゼラチン質を味わうと絶品です。


雲丹(ウニ)
「日本人はウニが大好き」世界で採れるウニの8割は日本で消費されていると言われています。
ウニは海の岩場などに生息し、全国の海に分布し、その種類は日本近海でも180種類で、なんと世界では1000種類も数えられます。中でも食用とされるのは、ほんの一握りにしかすぎません。
漁獲量ではアメリカが一番で日本は二番で、次にチリ・ロシア・カナダの順です。日本国内では北海道が最も多く、国内のウニには冷水系の「エゾバフンウニ」「キタムラサキウニ」で暖水系では「バフンウニ」「ムラサキウニ」「アカウニ」亜熱帯系の「シラヒゲウニ」と6種類あります。
ウニの食べ方には色々とありますが、寿司ネタのような生食とか焼いてある加工ウニとか「海胆、雲丹、海栗」いずれもウニと読みますが一般的には海胆・海栗は生の状態で雲丹は粒ウニ練りウニのような加工品を意味します。
ウニは老化予防・ガン予防などの効果と血行を良くする働きがあり、冷え性の方には特にお勧めです。
牛肉(エスニック風冷麺)
麺類
牛薄切り肉 200g
にんにく(すりおろす)1/2片
しょう油 小さじ2
こしょう 適量
サラダ油 大さじ1
ピーナッツ(粗めに刻む) 大さじ4
ミント 適量
青しそ 4枚
キュウリ 1/2本
サニーレタス 2枚
紫玉ねぎ 1/2個
もやし 1/2袋
しょう油 大さじ3
にんにく 1/4片
赤唐辛子(種を取ってみじん切り) 1本
砂糖 大さじ1と1/2
酢 大さじ4
水 大さじ2
ミント、青しそは食べやすい大きさにちぎる。キュウリは縦半分に切って斜め薄切りに、サニーレタスは細切りに、紫玉ねぎは薄切りにする。もやしはひげ根を取ってサッとゆでて冷ます。
たれの材料を混ぜ合わせておく。
牛肉は食べやすく切り、にんにく、しょう油、こしょうで下味をつけフライパンにサラダ油を熱して牛肉を焼く。
鍋にタップリの湯をわかして麺をゆで、冷水とって水気を切る
器に4の麺を盛り、ピーナッツをのせ2のたれをかける


さくらんぼ
国内産のさくらんぼは、早くは2月頃からハウス栽培の品が極く少量ずつ入荷してきます。
ハウス栽培は5月頃が最盛期になり、‘高砂‘佐藤錦‘などの優良品種が出回り、味・品質・大きさの面でも露地栽培を凌ぐ素晴らしい品(正し価格は高額)が入荷され、贈答用や高級料亭などの水菓子として重宝されています。
露地栽培は6月下旬から7月初旬が山形産の出回り頃となり、いずれも高砂種から佐藤錦種、ナポレオン種の順に品種が移り変わって行き、6月中旬から下旬が一番リーズナブルな頃と思います。
但し、さくらんぼは特に、天候によって品質及び収穫量が左右され、梅雨時の特に雨の多い年などは品質の良い状態のものを、お値打ち価格で店頭に並べるのに大変苦労します。
産地も最近では大型の雨除けハウスなどの設備にて品質・収穫の安定に努めています。
ただ、この様に旬の時期が短く天候にもデリケーな果物だけに、真っ赤に熟した小さな実を口にした時の感動や季節が感じられるのかもしれません。
一方の輸入さくらんぼに関しては、5月初旬のカルフォル二ア産早生種(ごく少量)、中旬以降は同産ビング種、6月中旬以降はワシントン産ビング種と移り変わり、約90%が航空便にて輸入されています。
最盛期は5月下旬から7月下旬で国内産の半値から約1/3の価格で販売されています。糖度も高く大粒ですが鮮度(空輸といっても日本の食物検疫など通関があ切れるまで数日かかる)・選別(アメリカでは日本程キメの細かい選別はしていない)の面では、日本のそれより少しばかりおちるものと思われます。
いずれにしても、バリューフォープライスの面では非常に優れたものですので、今後問題点を改善していけば、もっと人気は出るものと思います。又極く少量ながら、オーガニック(有機栽培)のレーニア種という大粒で味の良い品種も入荷され、輸入フルーツの新しい提案も出て来ています。
キャベツ
日本には18世紀ごろ、オランダ人によって長崎に伝えられたとの事。最初は観賞用だったのが、明治に入り食用に作り始めたそうです。
ただし、現在のように需要はありませんでしたが、今や野菜の中で取扱量は一番です。
1月~5月頃に出てくる春キャベツは、やや巻きがゆるく葉脈も柔らかく水分が多いので生食向きです。ロールキャベツなどには向きません。
価格は11月~3月ごろまでが安く、高くなるのは真夏のものです。ただし真夏の群馬、長野あたりの高原キャベツはおいしいものです。
昼夜の温度差がある産地のものが甘味があり、また葉が紫がかったものは寒さにあたったもので甘味があります。
保存はビニール袋に入れて冷蔵庫がいいでしょう


北海道産 塩紅鮭
毎年5月末頃から新物が入荷し、7月末頃まで漁があります。「北海道産」と言いますが、実際には、千島列島で漁獲されるロシアに母川を持つ紅鮭です。まだ回遊中の紅鮭ですので脂の乗りが良く、捕って直ぐに塩漬けにしておりますので鮮度も良い状態で市場に出回ります。
新物は、まだ塩が効いておらずやや甘塩で、紅鮭の甘みや美味しさが際立っています。初夏に食べたい魚のひとつです。
冬瓜(とうがん)
冬瓜のみぞれあんかけ
※ポイント
だしをたっぷり多いめに!!煮崩れのないように中火でゆっくりと煮る。
まず冬瓜を一口サイズに切る。次にだし(酒、コンブ、カツオ)を作り、その中に切った冬瓜を入れる。そして中火でゆっくりと煮る。
冬瓜が柔らかくなって来たらザルに移す。
カタクリ粉でまぶして油でさっと上げる。
こがさないように約160度に沈めた冬瓜が浮いて来たらさっとあげる。
下ゆでに使った出し汁にかしわのミンチをいれよくほぐす。
酒、砂糖で味を付け、冬瓜のアンを作る。(カタクリ粉か、吉野くず、どちらでもよい)
仕上にゆでたアスパラかチンゲン菜などをかるくまぶして出来上がり。大根おろしと生姜を香にまぶすと、なお美味しい。是非お試し下さい。

西瓜(すいか)
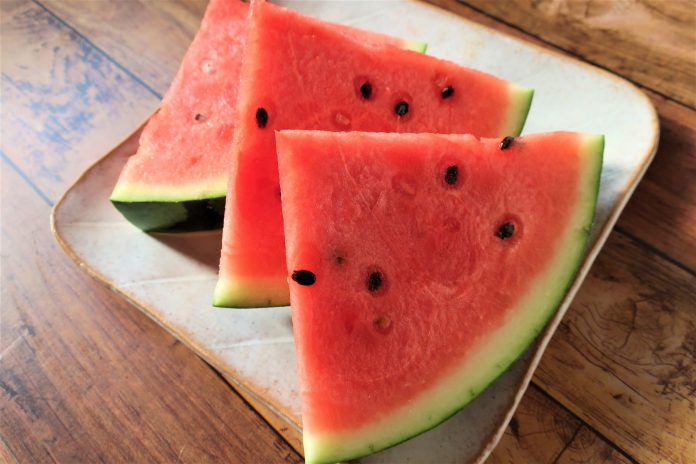
しかし、わが国に入って三百年以上珍しい果物という程度で大衆化せず、瓜類では、むしろ”まくわ瓜”が一般的でした。大衆化しなかった理由は、当時の西瓜は今の半分くらいの小型で皮が黒く、赤肉で瓜臭く、あまりうまくなかったからといわれています。
西瓜が一般の人にも美味しいと認識されたのは、明治に入ってからでアメリカの優良品種を導入するとともに、改良が重ねられ、ついに奈良で大和西瓜ができるに至って夏の果物の王者として、広く食べられるようになったのです。大正時代のことだそうです。
このように多種多様の品種があるのが西瓜の特徴ですが、現在の産地としては鳥取、福井、千葉など砂地の多い地域が代表的産地として挙げられるようです。
西瓜は栽培した畑に翌年も植えると生育が悪く、収穫量は減少します。これを「いや地」と言いますが、根菜類、果菜類にはこんな傾向が多いそうで、栽培する農家は毎年畑を変える必要があります。
しかし西瓜の場合は、いや地の年数が長いところから、代替えの畑もそう多くありません。そこで考えられたのが、カボチャの根につぎ木をする栽培方法です。瓜科の中でも南瓜(カボチャ)は、いや地は無いのが特徴で、これを利用し、今では西瓜はすべて苗の双葉の時代に芽先を切って、それをカボチャの芽を除いた所へ接ぎ木して苗を育て、これを連年同じ畑に植えています。
近年では台木にする作物も、ユウガオなども使われて安定した生育が望めるようになりました。この方法は、胡瓜、白瓜、メロンにも同様に使われているそうです。
暑い夏は西瓜の当り年
暑い日照りの続く夏は西瓜の当り年です。さしずめ梅雨が短く、雨の少ない年は、西瓜の故郷は炎熱のアフリカ、カラハリ砂漠であることを思えば納得がいきます。
西瓜は一年生の地面を這うつる草で、西瓜の栽培には高温乾燥が条件で、土壌は排水の良い砂土、砂壌土が良く、粘土質の場所での栽培は、大きくはなるものの成熟が遅く、従って品質は悪くなるそうです。
親づるが伸び始めてから間もなく、各葉の付け根から子づるが出て、それに一番果がなります。雌雄異花ですが、品種によっては雌しべ、雄しべを備える完全花をつけるものもあります。ミツバチなどによる虫媒体で、早朝に咲いて昼頃には受精能力を失い、開化三十日くらいで熟します。
牛肉(冷しゃぶ梅わさびだれサラダ)
牛肉(薄切り) 300g
なす 3本
ししとう 12本
ミニトマト(半分に切る)10コ
クレソン(3等分に切る) 1束
オリーブオイル 小さじ1
酒 大さじ1
塩 少々
梅干(たたいてペーストにする) 大1個
にんにく(すりおろす) 1/2片
酢 大さじ2
しょう油 小さじ1
練りわさび 小さじ1
オリーブオイル 大さじ2
たれの材料をすべてボウルにいれて混ぜ合わせる。
鍋に湯を沸かし、オリーブオイル、塩、酒を入れる。役80℃に冷まし薄切り肉を入れる。ピンク色に足ったら取り出し水気を取る。1のタレの半量に漬け込む。
ナスは7mm幅の輪切りにし、ししとうは竹串などで1~2ヶ所に穴を開ける。トースター又は魚焼きグリルで両面に焼き色がついたら残りのタレに漬ける。
2,3、ミニトマト、クレソン、タレを合わせてさっくりと混ぜ合わせる。


鰻(うなぎ)
日本の料理で大事なことは、季節感・色彩・味覚で、緑・赤・黄・白・黒の5色と酸味・苦味・甘味・辛味しおから味の五味で盛り付けも美しくておいしくて、栄養バランスも抜グンの料理ができる。
ちなみに調理法は五法といって「生・焼・煮・蒸・揚」これが基本である。
この時期は水分をよく取るため、食欲が落ちて、夏バテしやすいが、こういう時は、ヌルヌルやネバネバの食材がよい。うなぎ・ハモ・タコ・山芋・オクラetc.栄養分も多いしのどごしもよい。
私が小さい頃はうなぎのおなか部分が黄色いものが多かったが、今はほとんど白っぽい。これは天然と養殖の一番のちがいで、今は9割以上が養殖になっている。
養殖のなかでも浜名湖は有名で、これを関東では、背開きにし、焼いてから蒸すのが主流で関西は、腹開きをして、つけダレで焼く。まあ、どちらもうまいが個人的には、関東風がやわらかく、皮くさくないので好きである。
昔、私がうなぎ料理でいち番おいしかった料理を1つ紹介しましょう。セロリをゆばで巻いて、これをまたうなぎで巻き八幡巻き風にする。そして、つけダレで、網か鉄板で輪切りにしてやく、最高に美味です。
毛がに
カニと言えば、松葉カニやタラバガニを思い浮かべますが、北海道のカニと言えば、やはり毛ガニでしょう。 身の甘みが強く、味噌の味は濃厚、カニの本場北海道で一番人気と言うのも納得します。
旬は、春から夏と言われますが、一年を通して漁獲されいつでも食べられるカニです。
活けカニは、3%の食塩水を沸騰させ20分程湯がいてお召し上がりください。お薦めの食べ方は、ほぐした身にカニ味噌を付けて食べるのが一番美味しい。 その他、味噌汁、炊き込みご飯、グラタンにしても美味しく召し上がっていただけます。


豚肉のしぐれ煮 黒酢しょうが風味
材料
豚ロース肉(薄切り) 200g
新玉ねぎ(すりおろす) 大さじ1強(1/4個)
しょうゆ 大さじ3
黒酢 70cc
赤唐辛子(種を取る) 1本
しょうが 1片
酒 80cc
みりん 50cc
作り方
豚肉に新玉ねぎをもみこんで焼く10分置き、しょう油大さじ1を加え、さらにもみ込む。
鍋に黒酢、赤唐辛子、しょうが、酒、みりんを入れてひと煮立ちさせる。1を加えて2分ほど煮て残りのしょうゆを加えて8分ほど煮汁を飛ばすように煮る
水なす
皮が柔らかく、その名の如く、絞れば水が出るほどに、豊富に水分を含む、漬物に最適な茄子とされる大阪府産、水なす漬け、本格的なシーズンを迎えています。
水なすは、江戸時代初期から、泉州地域で栽培され、泉州の農家では、夏の豊作業で渇いたのどをうるおすために、水の代わりに水なすを食べていたとも言われています。とてもジューシーで浅漬けにすると最高です。
<水なす一夜漬け/ぬか床の作り方>
ぬか1kgに対して水1rを軟らかくぬって、塩200gとまぜる。さびた古くぎを5~6本布で包み、糸をかけたものを中に2~3個入れておく。
<水なす一夜漬け/漬け方>
水なすに塩を優しくすりつける。
よくまぜたぬか床に1を入れる。
夕方漬けて、翌朝出すと丁度よい。
※食べ方
昔から包丁で切るよりも、手で縦に大きくさいて食べるとよいと言われています。


鱧(ハモ)
過ごしやすい季節も終わりになり、初夏を迎えるにあたって日本独特の四季”梅雨”でありますが、中にはうっとうしい雨と思われる人が多いことと思われます。
ところで、海の中では美味しい食物が育っているのを皆様はご存知ですか?夏の魚の代表といえば「ハモ」ですが、そのハモが生存しているところは、ヒラメやカレイと同じ砂地の所であり、水温の低い場所にいます。
ハモの名産地といえば、淡路島から少し離れた沼島というところです。そこは大変波が荒く海流も激しい所です。今では九州地方の対馬や五島列島の品物も良いとされてます。
ニュースで報道された韓国産や中国産の輸入物が市場に多く出回っているようです。その理由の1つとして、韓国や中国の海は、水質や温度がハモにとって最適な条件であると思われます。また、品質的に大変脂質もあり、美味しいとされているようです。
ではなぜ梅雨と結びつくか?といえば、その気候を境に、ハモは卵を持つことによって身の質が変化し、脂質も多くなるから美味しくなるわけです。
ハモの特色として、大変骨が荒く”骨切り”という料理法が必要です。その後、熱湯を使用してハモチリをするのが代表的な召し上がり方です。
最近では、夏でも”ハモ鍋”という食べ方も多くなっています。また、新しい料理法としてハモあぶり、ハモ造りという召し上がり方もあり天婦羅なども梅肉を使用し、暑い夏には、さっぱりとした口当たりが良いと思われます。
中には、ハモフライや木の芽焼き(照り焼き)が好まれる人も多くおられます。今年の夏には一度変わった料理法で、挑戦してみてはどうでしょうか?

